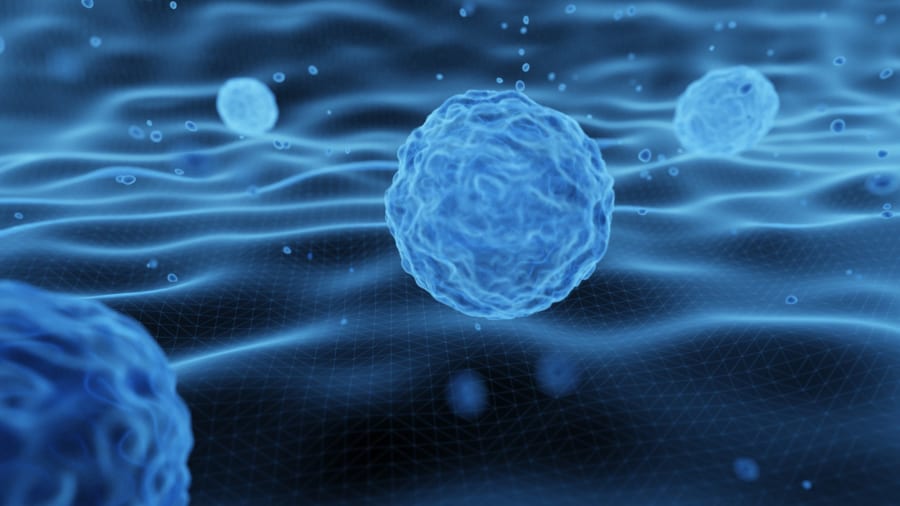2006年、皮膚などの体細胞から
iPS細胞(人工多能性幹細胞)が
樹立されたニュースは、
再生医療に大きな衝撃をもたらしました。
自分自身の細胞をいったん幹細胞状態に戻し、
そこから心筋や神経など、
さまざまな臓器・組織の細胞へ分化
できる道が開けたからです。
その後も「ES細胞(胚性幹細胞)」を含む
幹細胞をベースとした技術が急速に進歩し、
臓器オルガノイドや創薬スクリーニングへの
応用が盛んに検討されてきました。
しかし、こうした技術の多くは基本的に
「皮膚細胞などを一度は
幹細胞状態に変化させる」
必要があるため、
腫瘍化のリスクや増殖制御の難しさ、
さらには時間やコストの
問題などがつきまといます。
また、いったんリセットされた幹細胞だと
“年齢相応の細胞”としての特徴を失うため、
たとえば高齢者特有の神経変性疾患を
再現する際にうまくいかない場合もありました。
このような背景から近年脚光を浴び始めたのが、
「幹細胞を経由しない
直接リプログラミング」という考え方です。
もし皮膚線維芽細胞などを
中間段階なしで神経細胞に
変えることができれば、
リスクの低減や効率の大幅向上、
さらには細胞の“加齢状態”を
保持したまま変換することが期待できます。
ただし、
これまでの直接変換に挑んだ研究では、
変換効率や細胞の成熟度にばらつきが目立ち、
実用レベルで大量のニューロンを得るには
未解決の課題が多いのも事実でした。
そこで今回研究者たちは、
運動ニューロンの生成を担う
複数の転写因子に着目し、
その発現バランスや“細胞がどのタイミングで
分裂するか”といった
増殖履歴まで合わせて制御し、
皮膚細胞を効率的かつ大量にニューロンへ
直接変換する新手法を試みたのです。
調査に当たってはまず、
皮膚の線維芽細胞に
「運動ニューロンになるためのスイッチ」を
まとめて組み込み、
一気に“別モノの細胞”へ
変えてしまおうという仕組みづくりが行われました。
具体的には、
ベクター(遺伝子の運び屋)を使って
複数の転写因子を一度に導入し、
それだけでなく
「いつ細胞に入れるか」
「どの順番で並べるか」など、
細かなタイミングと組み合わせを工夫しました。
なかでもユニークなのが、
細胞が“ハイパー増殖”という
短い時間で一気に分裂する
状態をわざと利用した点です。
普通は細胞分裂が盛んなほど、
入れたタンパク質(転写因子)が
薄まってしまうように思うかもしれません。
ところが、
増殖が活発な時期は細胞のDNA(染色体)が
“開きやすく”なり、
それだけ転写因子が働きやすいという
現象がわかりました。
いわば「ドアが開いているうちに、
神経に必要なスイッチを一気に
入れてしまう」イメージです。
その結果、
もともと皮膚だった細胞が一気に
運動ニューロンの遺伝子プログラムへ
切り替わるのです。
さらに、
マウスだけでなくヒト成人の
皮膚細胞でも同様のアプローチを試みた結果、
幹細胞を介さずにニューロンへの
変換を確認することに成功しています。
幹細胞をはさまないことで
腫瘍化のリスクを相対的に抑えられると
期待されるだけでなく、
“細胞の年齢”をそのまま保ったまま
リプログラムできる可能性も示唆されており、
今後の応用研究がいっそう注目されています。
おもしろいのは、
この「増殖履歴のコントロール ×
転写因子のまとめ投入」という
組み合わせを突き詰めたことで、
わずか2種類のベクターだけでも
高い変換効率を実現できるようになったことです。
こうすることで、“ドアが開いているタイミング”に
合わせて転写因子を効率よく送り込み、
細胞内スイッチを同時にONにできます。
結果として、
実験室スケールで従来よりも
大幅に多くのニューロンを安定して
作り出せる可能性が示されました。
直接変換技術がもたらす革新
直接変換技術がもたらす革新
今回の成果は、
細胞の運命を決定づける転写因子の働き方や、
細胞が増殖するタイミングといった
要素を「うまく噛み合わせる」ことで、
幹細胞を経由せずにニューロンを
作り出せることを示しています。
これにより、
これまで問題視されてきた
腫瘍化リスクの低減や、
細胞の加齢状態を保持したままの
リプログラムが期待できるのは大きなメリットです。
たとえば、
加齢とともに進行する神経変性疾患の研究では、
患者の年齢相応の細胞を直接ニューロン化することで、
リアルな病態モデルを得られる可能性があります。
ただ幹細胞を経由しないとはいえ、
ベクターの使用や増殖制御因子の導入など、
新しいリスクや技術的ハードルも考えられます。
大量に得られたニューロンが実際に
長期間にわたって機能し続けるのか、
動物モデルや将来的には臨床の場で
どのようにふるまうのかを確認する必要があります。
今回の手法によって、
実験室スケールで大幅に効率が
上がったことは事実ですが、
“安全性”と“安定した機能”を両立させるための
検証はまだ続けていかなければなりません。
一方で新たな手法を使えば、
運動ニューロン以外にも、多様な
神経細胞やその他の細胞種へと
応用を広げられるかもしれません。
転写因子の組み合わせやタイミングを
自在に設計できるなら、
将来的には
「どの細胞を、どの細胞へでも」
直接変換できるようになる可能性もあります。
今回の研究は、
その第一歩となる革新的な
成果といえるでしょう。
再生医療や
難病研究を加速させる手法の一つとして、
今後さらに発展していくことが期待されます。