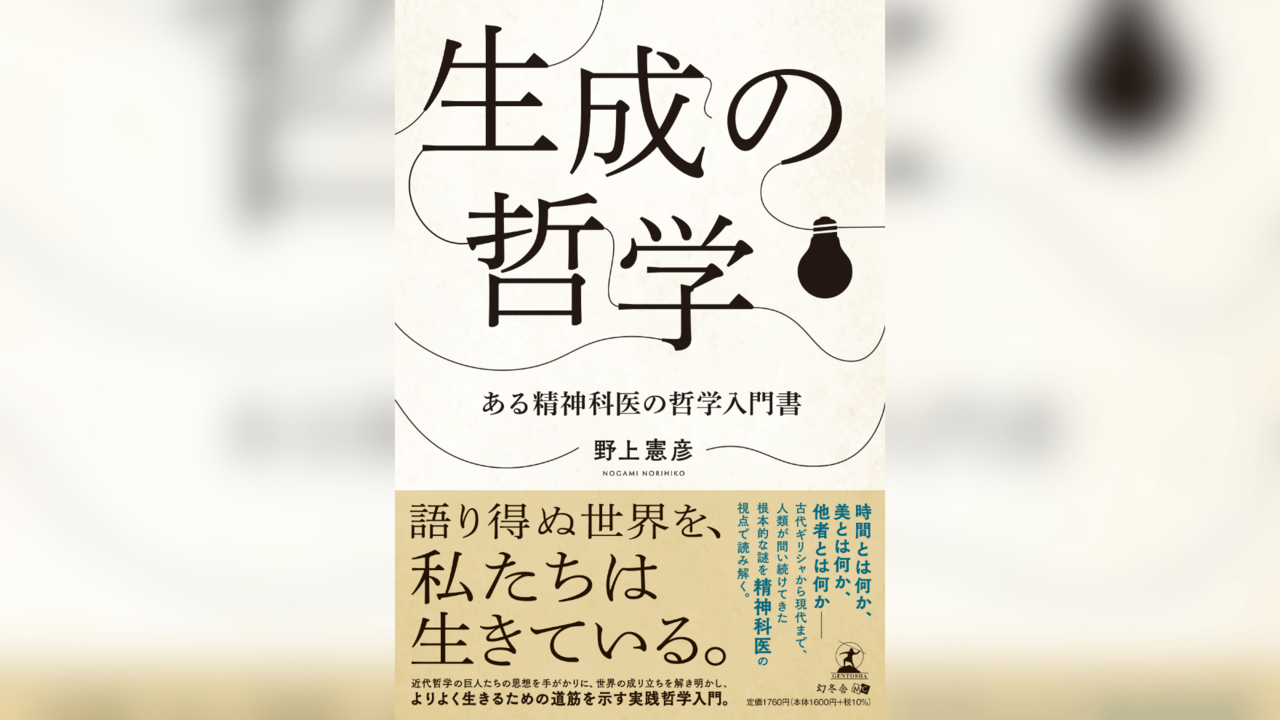はじめに
本書はコペルニクス的転回の書である。
コペルニクスは、
天動説から地動説へと転換させた人として有名であるが、
これにより地球(人間)は世界の中心ではなく、
多くある星の一つにすぎないことが主張された。
そして、
その後、
ガリレオ・ガリレイやニュートンなどの
活躍により、
科学的な世界観が形成されていき、
人間の外に対象としての物理的な世界が
広がっているという世界像が作り上げられていった。
コペルニクスは、
その出発点であったと思われる。
こうした背景のもとで、
カントは哲学におけるコペルニクス的転回を
行ったと主張した。
では、カントのコペルニクス的転回とは
どういう意味であろうか。
カントはコペルニクスから約150年程後の人であり、
近代物理学の完成者と言われる
ニュートンからも100年近く差のある人であった。
この間に、
科学は大きく進歩し、
またそうした知識をもとに技術も発展し、
カントの時代は産業革命がおこりつつある時代であった。
こうした時代のなかでカントは
物理学などにも非常に詳しい人であった。
そのようなカントがコペルニクス的転回ということを
示したのはどういうことであったのか。
カントは、
物自体という言葉で絶対的真理
(神・あるいは物理学的絶体真理)を
人間は知ることはできないと証明したのである。
つまり、
カントはコペルニクスとは逆方向を向いているのである。
コペルニクスは人間が宇宙の中心ではなく、
人間の外部に真理があるとする
科学的思考の出発点であった。
しかしカントは逆に、
人間は人間の外部の絶対的真理を
知ることはできないとした。
人間にできるのは自分の理性によって物事の正しさ、
善悪、美しさを判断できるだけであるとしたのである。
人間は理性により世界像を作り上げるだけであり、
世界の絶対的真理を知ることはできないと主張し、
これをコペルニクス的転回と呼んだのである。
確かにこれは全く新しい世界像の転換であった。
誰も考えつかない独創だと言えるだろう。
そして、その延長に、
フッサールの現象学、ニーチェの力の思考、
竹田の欲望論とつながっているのである。
絶対世界はない。
あるのは生き物の身体
(欲望・知覚・脳・理性)であり言葉であり、
人はそれに基づいて自分たちの世界像を作り上げ、
それを共有して生きていくのだと言える。
このように絶対真理を破棄し
、人間による世界像の形成という転回こそが
新しいコペルニクスの転回なのである。
そのことを、
これから述べていこうと思うのであるが、
うまく伝わればと願っている。
1 近代哲学の流れ
ドイツ・フランスが哲学の中心地
本題を始める前に、
まずは哲学史について確認したい。
近代哲学はデカルトから始まったと言われている。
【我思うゆえに我あり】があまりにも有名な言葉であるが、
これは考えること、
つまり、自由な思考の重要性を強調すると
同時に人が疑うことのできない始発点としての
【我思う】だと考えられる。
デカルトの生きた時代は、
ヨーロッパでは旧教カトリックと新教プロテスタントが
血で血を洗う戦いを展開していた。
ドイツで始まった宗教内乱がヨーロッパ各国に
波及し国際紛争に発展した三十年戦争が
象徴するように混乱した時代を迎えていた。
一方において、
ニュートンに代表されるような
自然科学の発展も目覚ましいものがあった。
このような価値観の混乱の中で、
デカルトは疑うことのできないもの(確かなもの)を
考えの出発点にしようとして
【我思う】をあげ、
そこから皆が共通して納得できる哲学を
作り上げようとしたのだと思う。
それが成功したわけではないが、
デカルトの心意気はよくわかる。
次の世代のビッグネーム、
カントについて考えてみる。
18世紀のフランス革命直前の時期は
啓蒙の時代と言われ、
様々な思想家が輩出した。
その中でカントが最も有名だと思われる。
カントは絶対真理―神―物自体は知ることが
できないものだと証明した。
これによって神と決別した。
そして、
人は理性によって正しい判断を
することができる存在だと言った。
この神の不可知性の証明は、
当時のヨーロッパの人たちにショックを与えた。
街灯を全部叩き壊してしまい、
いかに街灯が大切であるかを唱えた人に例えられている。
カントは
「人は誰もが正しいと思うような
生き方をしなさい」と主張した。
しかし、
そうした道徳的な人が幸せになる保証はない。
ずるい人や嘘を言う人が得をすることも
多いだろう。
とするなら、
カントは神がいて、
正しい人が不幸にならないように
見守ってほしいものだと、
最後に神を持ち出している。